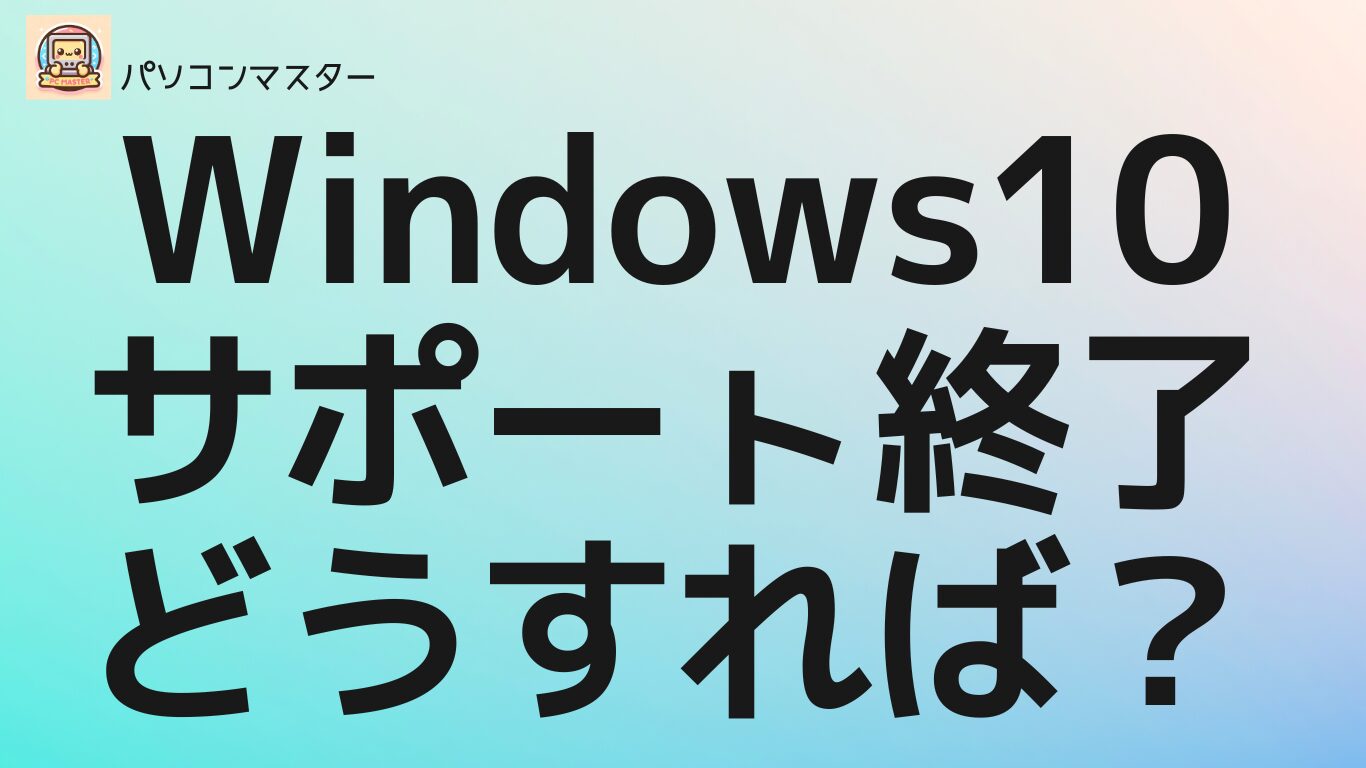Windows10 サポート終了の期限がいよいよ近づいています。Microsoftは2025年10月14日をもってWindows 10の公式サポートを終了すると発表しました。この日以降、Windows 10にはセキュリティ更新プログラムの提供が停止され、OSの脆弱性修正やメーカーサポートが受けられなくなります。では、これからどうすればいいのでしょうか?
そこで、本記事では、サポート終了の意味と影響、Windows11 アップグレードの方法や要件、アップグレードできない場合の対処(おすすめパソコンへの買い替え提案)、そして法人ユーザー向けの注意点まで、初心者にもわかりやすく解説します。最後によくある質問(Q&A)もまとめましたので、ぜひ対策の参考にしてください。
Windows 10サポート終了はいつ?その意味と影響
Windows 10のサポート終了日は2025年10月14日(火)です。この日を境に、Windows 10向けのあらゆるサポートが打ち切られます。具体的には、毎月提供されていたセキュリティパッチや不具合修正のWindowsアップデートが一切配信されなくなります。つまり、サポート終了後に新たな脆弱性やウイルス感染リスクが発見されても、修正プログラムが提供されない状態となります。OSの不具合に関するMicrosoftの無償・有償サポートも受けられなくなるため、問題が起きても自己解決するしかありません。
サポート終了の影響は無視できません。個人利用ではセキュリティリスクが格段に高まり、ウイルス感染や不正アクセスの被害に遭う可能性が増します。また、新しくリリースされるソフトやハードウェアがWindows 10をサポートせず、最新のソフトウェアやデバイスを利用できなくなる可能性もあります。例えば、今後発売されるプリンターやゲームなどがWindows 11以降のみ対応となり、Windows 10では動かないケースも出てくるでしょう。
業務で使用している場合はさらに注意が必要です。セキュリティ更新が止まった古いOSを使い続けることは、企業の情報漏えいやシステム停止リスクにつながります(詳細は後述の「法人向け注意点」で解説)。業務への影響としては、取引先から安全上の理由でWindows 10の使用を控えるよう求められたり、社内の規定やコンプライアンス上許可されなくなるケースも考えられます。こうしたリスクを避けるためにも、早めにWindows11へのアップグレードやPCの更新を計画することが重要です。
Windows 11へのアップグレード方法【無料で可能!】
Windows10からWindows11へのアップグレードは、条件を満たしていれば基本的に無料で行えます。Windows 10の正規ライセンスをお持ちで、お使いのPCが後述するシステム要件をクリアしていれば、追加費用なしでWindows 11にアップデート可能です。以下に、初心者でもできるWindows11 アップグレードの大まかな手順をまとめます。
- PCがアップグレード要件を満たしているか確認する – まずは現在お使いのパソコンがWindows 11に対応しているか確認しましょう。具体的なシステム必要要件と確認方法は後述しますが、Microsoftが提供する「PC正常性チェック」アプリを使うと簡単に診断できます。要件を満たしていない場合は、残念ながらそのPCにはWindows11をインストールできません(※非公式な方法で強制インストールする手段もありますが、サポート対象外となり推奨されません)。
- データのバックアップ – アップグレード作業を始める前に、大切なファイルや写真・文書などのデータをバックアップしておきましょう。通常、Windows 10から11へのアップグレードではデータやアプリは引き継がれますが、万一のトラブルに備えて外付けハードディスクやクラウドにバックアップを取っておくことを強くおすすめします。併せて、プリンターなど周辺機器の対応状況や、ウイルス対策ソフトなどインストール済みソフトの互換性も事前に確認しておくと安心です。古いソフトウェアの場合、Windows11で動作しない可能性があるため、事前に最新版へのアップデートや代替ソフトの検討も必要でしょう。
- Windows11にアップグレード開始 – 準備ができたら、いよいよアップグレード作業です。方法はいくつかありますが、一般的なのはWindows Update経由で行う手順です。Windows10の「設定」→「更新とセキュリティ」→「Windows Update」を開き、更新プログラムのチェックを行います。条件を満たすPCであれば、「Windows 11へのアップグレードを準備しています」あるいは「Windows 11を入手できます」といった案内が表示されます。その指示に従ってダウンロードとインストールを進めればOKです。アップグレードにはネットからのファイルダウンロードと再起動を伴うインストールが必要なため、1時間以上の時間とPCを再起動できるタイミングを確保して実施しましょう(ノートPCの場合は電源アダプターを繋いでおきます)。
- もしWindows UpdateにWindows11の案内が出てこない場合は、Microsoftの公式ツール「Windows 11 インストールアシスタント」や「メディア作成ツール」を使ってアップグレードする方法もあります。Microsoftの公式サイトからこれらのツールをダウンロードし、画面の指示に従ってインストールメディアを作成または直接アップデートすることでWindows11に移行できます。こちらの方法は多少手順が増えますが、Windows Update経由と結果は同じです。
- セットアップとアカウント設定 – Windows11へのアップグレード後、初回起動時に簡単なセットアップが入ります。個人利用の場合、Microsoftアカウントでのサインインが必要になる点がWindows10までと異なる部分です(Windows11 Homeは初期設定時にインターネット接続とMicrosoftアカウントが必須)。画面の指示に従ってアカウントでログインし、プライバシー設定などを完了させましょう。一度設定すれば、次回からは通常通りPCを使用できます。
アップグレード方法自体は以上ですが、「自分のPCが本当にWindows11に対応しているか分からない」という方も多いでしょう。次のセクションでアップグレードに必要な要件と、その確認方法について詳しく解説します。また、アップグレードできない古いPCをどうするかについても後ほど述べます。
なお、現在Windows 10をご利用中で、どうしてもWindows 11へのアップグレードに不安がある場合や、ライセンスをお持ちでない場合は、新たにWindows 11の正規ライセンスを購入するという選択肢もあります。市販されているWindows 11のパッケージ版やダウンロード版を購入すれば、新PCへのクリーンインストールや仮想環境での利用も可能です。例えば、以下のようなWindows 11製品が販売されています。
- Windows 11 Home 日本語版(パッケージ版/ダウンロード版) – 個人向けエディション。自作PCやOS無しPCにインストールする場合に購入します。Windows 11 Home 日本語版 (Amazon) などで入手可能です。
- Windows 11 Pro 日本語版 – 主に法人や上級者向けエディション。Homeにはない高度な機能(ドメイン参加やBitLockerなど)が必要な場合に選びます。
ただし、既にWindows 10をお使いであれば、上記のようなOSを新規購入しなくても無料アップグレードができますので、基本的には新たな出費は不要です。
Windows 11のアップグレード必要要件と確認方法
Windows11へのアップグレード要件を満たしているかどうかは、事前に必ず確認しましょう。Windows 11はWindows 10に比べていくつか厳しいシステム要件が設定されています。主な必要スペックは以下の通りですmicrosoft.com:
- CPU(プロセッサ): 64ビット対応のプロセッサで、1GHz以上・2コア以上の性能が必要です。具体的には、Intel製CPUなら第8世代以降のCore iシリーズや同等のPentium/Celeron、AMDなら第2世代以降のRyzenシリーズなどが該当します。それ以前の古いCPU(2017年以前のモデル)は原則サポート外です。
- メモリ: 4GB以上(64ビットOSのため、最低4GB必要)。
- ストレージ容量: 64GB以上のストレージ空き容量が必要です。Windows11自体の容量要件であり、システムドライブ(通常Cドライブ)に十分な空きがないとインストールできません。
- システムファームウェア: UEFIでの起動、およびセキュアブートへの対応が必要です。古いBIOSモードでインストールされたOSの場合は、UEFIモードへ変換する必要があります。
- TPM: TPM 2.0(トラステッドプラットフォームモジュール)のサポートが必須です。これはセキュリティチップの一種で、2018年前後以降のPCには標準搭載されています。自作PCの場合はマザーボード設定でTPM(Intel PTTやAMD fTPM)を有効にする必要があります。
- グラフィックス: DirectX 12以上対応のグラフィックスカード(または内蔵GPU)で、WDDM 2.0ドライバーが必要です。ほとんどの近年のPCは満たしています。
- ディスプレイ: 9インチ以上・720p以上の解像度のモニターが必要(ノートPCなら問題ありません)。
上記を見ると専門用語も多いですが、「自分のPCが対応しているのか分からない…」という方は安心してください。Microsoft公式の診断ツール「PC正常性チェック」アプリを使えば、難しいスペック表を見なくてもワンクリックで判定できます。
PC正常性チェックアプリを利用すると、このように「この PC は Windows 11 の要件を満たしています」といった結果画面が表示されます。PC正常性チェックはMicrosoftが無償提供している公式アプリで、現在お使いのPCがWindows11のシステム要件を満たしているかどうか、自動でチェックしてくれるツールです。使い方は簡単で、Microsoftの公式サイトから「PC 正常性チェック」アプリをダウンロードしインストールします。アプリを起動すると上部に「Windows 11のご紹介」という項目があり、青いボタンの「今すぐチェック」をクリックするだけで診断スタート。【24】の画像は診断結果の一例で、要件を満たしている場合は緑色のチェックマークとともに「この PC は Windows 11 の要件を満たしています」と表示されます。逆に要件を満たしていない場合は、足りない項目(例えば「TPMが有効になっていません」「プロセッサがサポート対象外です」など)が明示されます。結果画面で何が原因で非対応なのかが分かるので、アップグレード可能かどうか一目で判別できます。
もしPC正常性チェックの結果、「このPCはWindows11を実行できません」と表示されてアップグレード非対応と判定された場合、そのPCでWindows 11を動かす公式な方法はありません。この場合は、次章で説明するようにパソコン買い替えを検討する必要があります。一部にはレジストリ変更などでWindows11を強制インストールする非公式手段も存在しますが、そうした方法は将来の更新が保証されず推奨されません。基本的には、要件を満たさないPCで無理にWindows11を使うのはリスクが高いと心得ましょう。
補足: Windows10からWindows11へのアップグレードを行うには、Windows10自体がある程度新しいバージョンである必要があります。Windows10 バージョン2004以降であれば直接Windows11へアップグレード可能ですが、もし長期間アップデートしておらずWindows10の古いバージョン(例えば1507や1607など)のまま使っている場合、一度Windows10の最新アップデート(22H2)まで適用してからでないとWindows11への更新オプションが出ない可能性があります。通常Windows Update経由で最新状態にしておけば問題ありませんが、「Windows11へのアップグレードがWindows Updateに表示されない」という場合は、まずWindows10自体のアップデート不足がないか確認してください。
アップグレードできない場合の対処:おすすめパソコンへの買い替え
PC正常性チェックの結果、システム要件を満たさずWindows11にアップグレードできないPCだった場合はどうすれば良いでしょうか? その場合、基本的にはパソコンの買い替えを検討することをおすすめします。サポート終了後のWindows10を使い続けるリスクを考えると、対応していない古いPCには見切りをつけて、新しいWindows11対応PCに移行するのが安心・安全だからです。
新しいPCであれば最初からWindows 11がインストールされた状態で出荷されていますし、性能や省電力性も向上しているため今後数年間は快適に利用できます。ここでは、現在入手可能なWindows11搭載のおすすめパソコンをいくつかご紹介します。用途や予算に応じて参考にしてみてください(いずれもAmazonリンクを掲載しています)。
富士通 ノートパソコン FMV Lite WA1/J2 (MS Office 2024/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) AHシリーズ FMVWJ2A152_AZ
富士通のノートパソコン「FMV Lite WA1/J2(FMVWJ2A152_AZ)」は、15.6型フルHD液晶、Windows 11 Home、インテル Core i5、16GBメモリ、512GB SSDを搭載し、Microsoft Office Home & Business 2024が付属。日常使いからビジネスまで快適に対応する高性能モデルです。
富士通のノートパソコン「FMV LIFEBOOK WAA/J2(FMVWJ2AA72_AZ)」
富士通のノートパソコン「FMV LIFEBOOK WAA/J2(FMVWJ2AA72_AZ)」は、15.6型フルHDスーパーファイン液晶を搭載し、AMD Ryzen™ 7 5700U モバイル・プロセッサ、16GBメモリ、512GB SSD、DVDスーパーマルチドライブを備えています。Windows 11 HomeとMicrosoft Office Home & Business 2024がプリインストールされ、日常利用からビジネス用途まで快適に対応する高性能モデルです。
HP ノートパソコン HP 15-fd インテル第13世代 インテル Core i5-1334U 16GBメモリ 256GB SSD Bluetooth 指紋認証 薄型 ナチュラルシルバー Office搭載 1年間メーカー保証
HPのノートパソコン「HP 15-fd」は、インテル第13世代Core i5-1334Uプロセッサー、16GBメモリ、256GB SSDを搭載し、日常の作業からビジネス用途まで快適に対応します。15.6インチのフルHD非光沢IPSディスプレイは、映り込みを抑えつつ鮮やかな表示を実現。指紋認証センサーやWi-Fi 6対応、Bluetooth接続など、利便性とセキュリティも充実しています。薄型・軽量なナチュラルシルバーボディはスタイリッシュで持ち運びにも便利です。Microsoft Officeがプリインストールされ、すぐに作業を開始できます。1年間のメーカー保証付きで、安心してご利用いただけます。
上記のようなWindows11対応PCに買い替えることで、2025年10月以降も安心してパソコンを使い続けることができます。特に古いPCではハード自体の寿命(HDD故障やバッテリー劣化など)も心配な時期です。このタイミングで新調すれば、今後5年以上はOSサポートとハード両面で安心感を得られるでしょう。
買い替えの際は、現在使っているデータの移行もお忘れなく。古いPCから新しいPCへは、外付けHDDやUSBメモリ、クラウドストレージを使ってファイルをコピーしたり、MicrosoftアカウントでOneDrive同期を利用するとスムーズに引き継げます。また不要になった古いPCは、初期化してから廃棄(または下取りや譲渡)するようにしましょう。
法人ユーザー向け注意点 – 業務ソフト互換性・セキュリティ・複数台管理
企業や団体で多数のPCを管理している法人ユーザーの場合、Windows 10サポート終了への対応は計画的に進める必要があります。個人利用以上に考慮すべきポイントが多いため、特に以下の点に注意して準備を行いましょう。
- 業務ソフトや周辺機器の互換性確認: 社内で使用している業務アプリケーション(会計ソフト、販売管理システム、勤怠管理ツールなど)がWindows 11上で正常に動作するか事前に確認してください。ベンダーからWindows11対応版の提供があるか、アップデートが必要かを調べます。古いバージョンのソフトウェアによってはWindows 11非対応の場合もあるため、必要に応じて最新版へのアップグレードや代替ソフト導入の検討が必要です。また、社内開発のシステムがある場合はテスト環境でWindows11上での動作検証を行いましょう。併せて、プリンターやスキャナー、特殊な機器のデバイスドライバーがWindows11対応かも確認し、メーカー提供の新しいドライバーがあるなら適用しておくことが大切です。
- セキュリティリスクへの対策: 業務用PCでWindows 10をサポート終了後も使い続けることは、重大なセキュリティリスクを招きます。サイバー攻撃者はサポート切れOSの脆弱性を狙ってくるため、ネットワークに接続された1台でもWindows 10のままだと企業全体の情報漏えいやランサムウェア感染の入口になりかねません。どうしても事情でWindows10を残さざるを得ない場合でも、Microsoftが提供予定の有償延長サポート (Extended Security Update) を検討する、ネットワークから隔離して使うなどリスク低減策を取るべきです。しかし延長サポートでもセキュリティパッチ以外の更新は提供されませんし根本解決にはならないため、可能な限り早期にWindows11へ移行することが望ましいでしょう。
- 複数台の一括アップグレードと管理: 社内にPCが多数ある場合、すべてを個別に手動アップグレードするのは非効率です。企業ではMicrosoftのエンドポイント管理ツール(たとえばWindows Update for BusinessやMicrosoft Intune、SCCM/Configuration Manager)を活用し、ポリシーを設定して段階的にWindows11へアップグレードすることができます。IT管理者が各PCの互換性情報を収集し、部署ごと・利用者ごとにスケジュールを組んで順次アップグレードを実施するのが良いでしょう。業務に支障が出ないよう、計画的なロールアウトとユーザーへの周知(新しいUIへの慣れ方ガイドなど)も欠かせません。台数が多く社内で手が回らない場合は、PCメーカーやSIerの提供するアップグレードサービスやITサポート企業へのアウトソーシングも検討しましょう。
以上のように、法人利用では「ソフト・ハードの互換性」「セキュリティ対策」「多数PCの管理」という観点で準備を進める必要があります。自社のIT資産棚卸しを行い、Windows10搭載PCが何台あるか、各PCがWindows11要件を満たすか(要件未達なら予算計上の上で買い替え計画を立てる)、社内システムで懸念事項はないか、などを総合的にチェックしてください。早めに動き出すことで、サポート終了間際になって慌てる事態を防げます。
よくある質問(Q&A)
最後に、Windows10サポート終了とWindows11アップグレードに関してユーザーから寄せられるよくある質問とその回答をQ&A形式でまとめました。
Q1. Windows 10のサポートが終了した後も、そのまま使い続けても大丈夫ですか?
A. 利用自体は可能ですが、おすすめできません。サポート終了後もWindows10搭載PCは起動しますし、既存のソフトもすぐに使えなくなるわけではありません。しかし、セキュリティ更新がないため日に日にリスクが高まります。インターネットに接続せずスタンドアロンで使うならともかく、通常のネット利用を続けるならウイルス感染や不正アクセスの危険性が非常に高くなります。また、新しい周辺機器やソフトが対応しない問題も出てきて徐々に不便になります。業務利用の場合は特にリスクが大きいので、Windows10を使い続けることは避けるべきでしょう。
Q2. Windows11へのアップグレードには費用がかかりますか?
A. 基本的に費用はかかりません(無料)。現在Windows10をお使いで、そのPCがWindows11の動作要件を満たしていれば、Windows11へのアップグレードは無償です。Microsoftが提供するアップグレードはWindows Update経由で順次案内されています。ただし、Windows10が正規ライセンスであることが前提です(海賊版やライセンス認証されていない場合は除く)。一方、お使いのPCがWindows11非対応で新しくOSを購入する場合や、Windows10以外の古いOS(たとえばWindows 7や8.1など)から直接Windows11にする場合は、新規にWindows11を購入する必要があります。この場合はWindows11のパッケージ版やDSP版ライセンスを購入する費用が発生します。いずれにせよ、対応PCならWindows10→11は追加費用なくアップグレードできますのでご安心ください。
Q3. 自分のPCがWindows11にアップグレードできないと言われました。何か方法はありますか?
A. PC正常性チェックで「このPCはWindows11を実行できません」と表示された場合、そのPCで公式にWindows11を動かす方法は原則ありません。対処法としては新しいPCへの買い替えが現実的な解決策になります。どうしてもそのPCでWindows11を使いたいという場合、インターネット上にはTPMやCPU要件を回避してインストールする非公式な手順も紹介されています。しかし、そうした方法は自己責任であり、将来のアップデート提供が保証されなかったり不安定になる恐れがあります。特に初心者の方や企業利用ではリスクが高いのでおすすめできません。やはりWindows11対応PCを用意するのが安全策です。買い替えの際は上述のおすすめパソコンも参考に、Windows11プリインストール機種を選ぶとよいでしょう。
Q4. Windows11へアップグレードするとデータやアプリは消えてしまいますか?
A. いいえ、通常は消えずに引き継がれます。Windows10からWindows11へのアップグレードは「上書きインストール」に近い形で行われるため、基本的にユーザーデータ(ドキュメント、画像、動画などのファイル)やインストール済みアプリケーションはそのまま残ります。アップグレード後もこれまで通りファイルにアクセスできますし、アプリも再インストール不要で利用できます。ただし100%保証されているわけではないため、念のため事前にバックアップを取っておくことを強く推奨します。また、一部のアプリは初回起動時に再設定が必要になったり、周辺機器のドライバーを再インストールするケースもあります。重要なデータさえバックアップしておけば、万一トラブルが起きても復元可能なので、面倒でもバックアップは必ず実行してください。
Q5. Windows11にすると使い勝手が大きく変わると聞きました。戸惑わずに使えるでしょうか?
A. UI(見た目)は変わりますが、基本的な操作はWindows10と大きくは変わりません。Windows11ではスタートメニューの位置が画面中央下に移動しデザインも刷新されています(設定で従来通り左下配置に変更可能)。タスクバーの挙動や右クリックメニューの表示方法など、一部インターフェースの違いはありますが、ファイル操作や設定画面の構成など基本は共通です。数日使えばすぐに慣れる程度の変更と言えるでしょう。むしろ動作の軽快さやセキュリティの強化、新機能(ウィジェット機能や仮想デスクトップ強化、スナップレイアウトによる画面分割配置など)による生産性向上などメリットが多いです。また、今後はWindows11向けの新機能アップデートやソフトウェアが中心になりますので、早めに新環境に慣れておく方が得策です。不安な場合は、アップグレード前にWindows11の画面レイアウト紹介記事やMicrosoftのガイドを一読すると良いでしょう。
2025年10月のWindows10 サポート終了まで残り時間は限られています。大事なPCとデータを守るため、そして快適なコンピューティング環境を維持するために、ぜひ早めのWindows11 アップグレードまたは新PCへの移行を検討してください。適切な対策を講じておけば、サポート切れによるセキュリティ不安やトラブルに悩まされることなく、これからも安心してパソコンを活用できるでしょう。今から準備を始めて、2025年10月を安心して迎えましょう!
この記事のポイント: Windows 10サポート終了の影響と対策、Windows11へのアップグレード手順と要件確認の方法、アップグレードできない場合のおすすめパソコン紹介、法人ユーザーが留意すべき事項、そしてFAQによる疑問解消を包括的に解説しました。この記事を参考に、ぜひ安全・快適なWindows11環境への移行を実現してください。